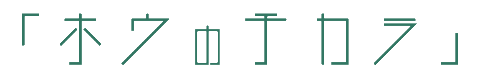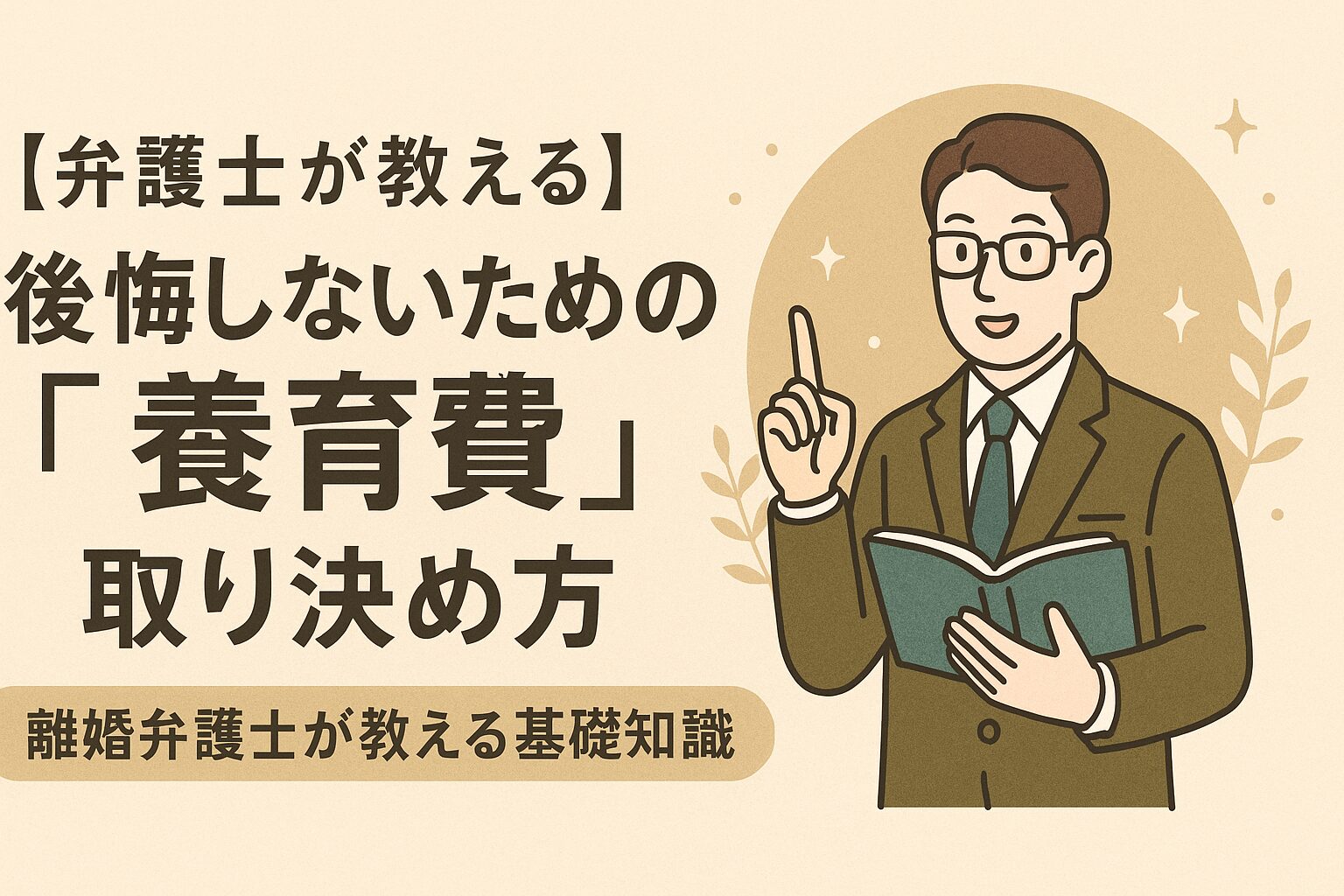「離婚後、子どものためのお金は、一体いくらもらえるのが妥当なの?」
「養育費の金額で揉めている…どうやって計算すればいいんだろう?」
「『支払う』と口約束してくれたけど、本当に大丈夫?将来が不安…」
お子さんがいる夫婦が離婚を決意したとき、財産分与や慰謝料と並んで、そして何よりも真剣に考えなければならないのが「養育費」の問題です。
養育費は、単なる親から親へのお金の移動ではありません。それは、親権を持つかどうかに関わらず、両親が等しく負うべき、子どもを育てるための大切な責任であり、子ども自身の健やかな成長のために不可欠な、子どもの権利です。
しかし、この養育費の取り決めを曖昧にしたために、離婚後に支払いが滞り、子どもとの生活に困窮してしまうケースが後を絶ちません。
この記事では、あなたとお子さんの未来を守るために、法律の専門家である弁護士監修のもと、後悔しないための養育費の取り決め方について、以下の点を詳しく解説します。
- そもそも養育費とは?いつまで、何が含まれる?
- 【相場がわかる】裁判所も使う「養育費算定表」の正しい見方と計算方法
- 相場以上に請求できる?養育費の増額・減額が認められるケース
- 【最重要】支払いを確保するための「公正証書」の絶大な効果
- 万が一、支払いが止まった場合の対処法
- 養育費の取り決めで弁護士が果たす役割
この記事を読めば、養育費に関する正しい知識が身につき、お子さんの未来のために、公正で、かつ確実な約束を取り付けるための具体的な方法が分かります。
目次
養育費とは?まず押さえるべき3つの基礎知識
養育費の話し合いを始める前に、基本的なルールを理解しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 養育費の目的 | 子どもが経済的に自立するまでに必要となる、衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費など、生活全般にかかる費用を分担するためのものです。 |
| ② 支払う義務者と期間 | 子どもと離れて暮らす親(非監護親)が、子どもと一緒に暮らす親(監護親)に対して支払います。期間は、原則として子どもが成人するまで(現在は18歳ですが、多くの場合は大学卒業を見据え「20歳まで」や「大学卒業の月まで」と取り決める)です。 |
| ③ 支払うべき金額の考え方 | 子どもの生活レベルが、親の離婚によって不当に下がらないよう、両親の収入に応じた生活レベルを維持できる金額を、双方の収入に応じて公平に分担するという考え方(生活保持義務)に基づきます。 |
重要なのは、養育費は「親の都合」で決められるものではなく、あくまで「子どもの利益」を最優先に考えるべきものだということです。
【相場がわかる】「養育費算定表」の正しい見方と計算方法
「では、具体的にいくら請求できるの?」という疑問に答える、客観的な基準が、裁判所が公開している「養育費算定表」です。実際の離婚調停や裁判でも、この算定表が基準として用いられます。
養育費算定表の仕組み
養育費算定表は、
- 支払う側(義務者)の年収
- 受け取る側(権利者)の年収
- 子どもの人数と年齢
という3つの要素から、標準的な養育費の月額が分かるように作られています。
算定表の具体的な見方(例)
【例】子ども1人(0~14歳)、夫(義務者)の年収500万円(給与所得者)、妻(権利者)の年収150万円(給与所得者)の場合
- 裁判所のウェブサイトで、該当する表「養育費・子1人表(子0~14歳)」を開きます。
- 表の横軸で、義務者(夫)の年収「500」のラインを探します。
- 表の縦軸で、権利者(妻)の年収「150」のラインを探します。
- その2つのラインが交差するマス目を見ます。この例の場合、「6~8万円」の範囲に入ります。
これが、このケースにおける養育費の相場となります。この「6~8万円」の範囲内で、具体的な金額を話し合っていくのが基本です。
▶ 養育費算定表(裁判所ウェブサイト)
※実際の算定表へのリンクをここに設置する想定です。
算定の基礎となる「年収」とは?
算定表で使う「年収」は、手取り額ではなく、税金などが引かれる前の総収入です。
| 働き方 | 確認する書類 | 見るべき項目 |
|---|---|---|
| 給与所得者(会社員など) | 源泉徴収票 | 「支払金額」 |
| 自営業者 | 確定申告書 | 「課税される所得金額」 (※実際の算出はより複雑なため弁護士相談推奨) |
相場以上に請求できる?養育費の増額・減額が認められるケース
養育費算定表はあくまで標準的なケースを想定したものです。個別の事情によっては、算定表の金額から増額または減額されることがあります。
増額が認められやすいケース
- 高額な学費: 子どもが私立学校や大学に通っており、その学費について双方の合意がある場合。
- 特別な医療費: 子どもに持病や障害があり、高額な治療費や介助費用が継続的にかかる場合。
- その他: 留学費用や、特別な習い事(才能を伸ばすためのものなど)で、支払い義務者も同意している場合。
減額が認められる可能性があるケース
- 支払い義務者の失業・減収: リストラや会社の倒産、病気など、やむを得ない事情で収入が大幅に減少した場合。
- 受け取る側の増収: 受け取る側が再婚し、その相手と子どもが養子縁組をした場合や、受け取る側の収入が大幅に増加した場合。
- 支払い義務者の再婚・扶養家族の増加: 支払い義務者が再婚し、新たに子どもが生まれるなど、扶養すべき家族が増えた場合。
一度決めた養育費も、このような事情の変更があれば、将来的に増額や減額を求める「養育費増減額調停」を家庭裁判所に申し立てることができます。
【最重要】口約束は危険!支払いを確保するための「公正証書」
養育費の取り決めで最も重要なことは、合意した内容を必ず法的に有効な書面に残すことです。口約束や、当事者同士で作成した簡単な念書だけでは、将来の不払いを防ぐことはできません。
| 離婚協議書(私文書) | 公正証書 | |
|---|---|---|
| 作成者 | 当事者本人(または弁護士など) | 公証人(法律の専門家) |
| 作成場所 | 自由 | 公証役場 |
| 証明力 | 当事者間で合意があったことの証明にはなる | 非常に高い証明力を持つ公文書 |
| 不払い時の強制力 | なし (別途、裁判を起こす必要がある) | あり(強制執行が可能) |
公正証書の絶大な効果
公正証書は、公証役場で公証人という法律の専門家が作成する公文書です。公正証書を作成する際に、「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」という一文を入れておくことで、その公正証書は判決と同じ効力を持ちます。
これにより、万が一、相手からの養育費の支払いが滞った場合に、改めて裁判を起こすという時間と手間をかけることなく、直ちに相手の給与や預金口座を差し押さえる「強制執行」の手続きに進むことができるのです。
子どものための大切なお金を、将来にわたって確実に確保するためにも、養育費の取り決めは必ず公正証書にしておくことを強くお勧めします。
万が一、支払いが止まってしまった場合の対処法
公正証書を作成していても、支払いが滞る可能性はゼロではありません。その場合は、以下のステップで冷静に対処しましょう。
- まずは直接連絡: まずは電話やメールで、支払いが遅れている旨を伝え、催促します。うっかり忘れているだけの可能性もあります。
- 内容証明郵便を送付: 直接の連絡に応じない場合は、弁護士に依頼するなどして、支払いを求める内容証明郵便を送付します。心理的なプレッシャーを与え、請求の意思を明確に示します。
- 家庭裁判所の手続きを利用: 家庭裁判所には、支払いを促す「履行勧告」や、支払いを命じる「履行命令」という制度があります。
- 強制執行(差押え): それでも支払われない場合は、最終手段として、地方裁判所に強制執行を申し立て、相手の給与や財産を差し押さえます。公正証書があれば、この手続きをスムーズに進めることができます。
養育費の取り決めで弁護士が果たす重要な役割
養育費の取り決めは、当事者同士でも可能ですが、弁護士に依頼することで、より有利で、かつ確実な解決が期待できます。
- 適正な金額の算定と交渉: あなたのケースにおける法的に妥当な養育費額を算定し、特別な事情(私立の学費など)があれば、それを上乗せできるよう、相手方と専門的な交渉を行います。
- 感情的な対立の回避: あなたの代理人として冷静に交渉を進めるため、お金の話で感情的になってしまい、話し合いが決裂するのを防ぎます。
- 不払い時の迅速な対応: 万が一、支払いが滞った場合にも、速やかに内容証明郵便の送付や強制執行の手続きに着手できます。
よくある質問(FAQ)
Q. 養育費の時効はありますか?
A. はい、あります。当事者間の合意で決めた養育費は、各支払期日から5年で時効になります。調停や裁判で決まった場合は10年です。ただし、時効が成立する前に請求すれば、時効の進行を止めることができます。未払いの養育費がある場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
Q. 養育費を一括で受け取ることはできますか?
A. 相手方が合意すれば可能です。将来の不払いのリスクがなくなるメリットがありますが、一括で受け取ると、相場よりも低い金額になったり、高額な贈与税がかかったりするデメリットもあります。慎重な判断が必要です。
Q. 相手の年収が分かりません。どうすればいいですか?
A. 話し合いの段階では、源泉徴収票や確定申告書を見せてもらうよう求めるのが基本です。相手が応じない場合、離婚調停や裁判になれば、裁判所を通じて開示を命じる「調査嘱託」などの手続きを利用することができます。
Q. 相手が再婚した場合、養育費は減額されますか?
A. 相手が再婚し、その再婚相手との間に子どもが生まれるなど、扶養すべき家族が増えた場合、養育費の減額を求める正当な理由となる可能性があります。その場合、相手から養育費減額調停が申し立てられることが考えられます。
まとめ:子どもの未来のために、養育費は「公正証書」で確実に
離婚は、親にとっては夫婦関係の終わりですが、子どもにとっては、これからも変わらず両親から愛情と支援を受ける権利があります。養育費は、その権利を経済的な側面から支える、極めて重要なものです。
後悔しない養育費の取り決め方のポイントは、
- 「養育費算定表」を基準に、客観的な金額を把握すること。
- 特別な事情があれば、増額の交渉を諦めないこと。
- そして何よりも、合意した内容は必ず「強制執行認諾文言付きの公正証書」として書面に残すこと。
この3つに尽きます。
感情的な対立や専門的な知識不足から、お子さんのための権利を不当に手放してしまうことのないよう、離婚問題、特に養育費の取り決めについては、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。専門家のサポートを得て、お子さんの明るい未来への道を、確実なものにしてください。
☑豊富な借金問題の解決実績
☑債務整理のエキスパート
☑クライアントに本気で寄り添う
☑あなたに合った解決方法を見つけられる
\専門家による本気のアドバイス/