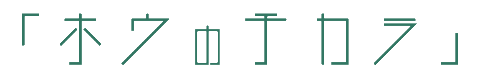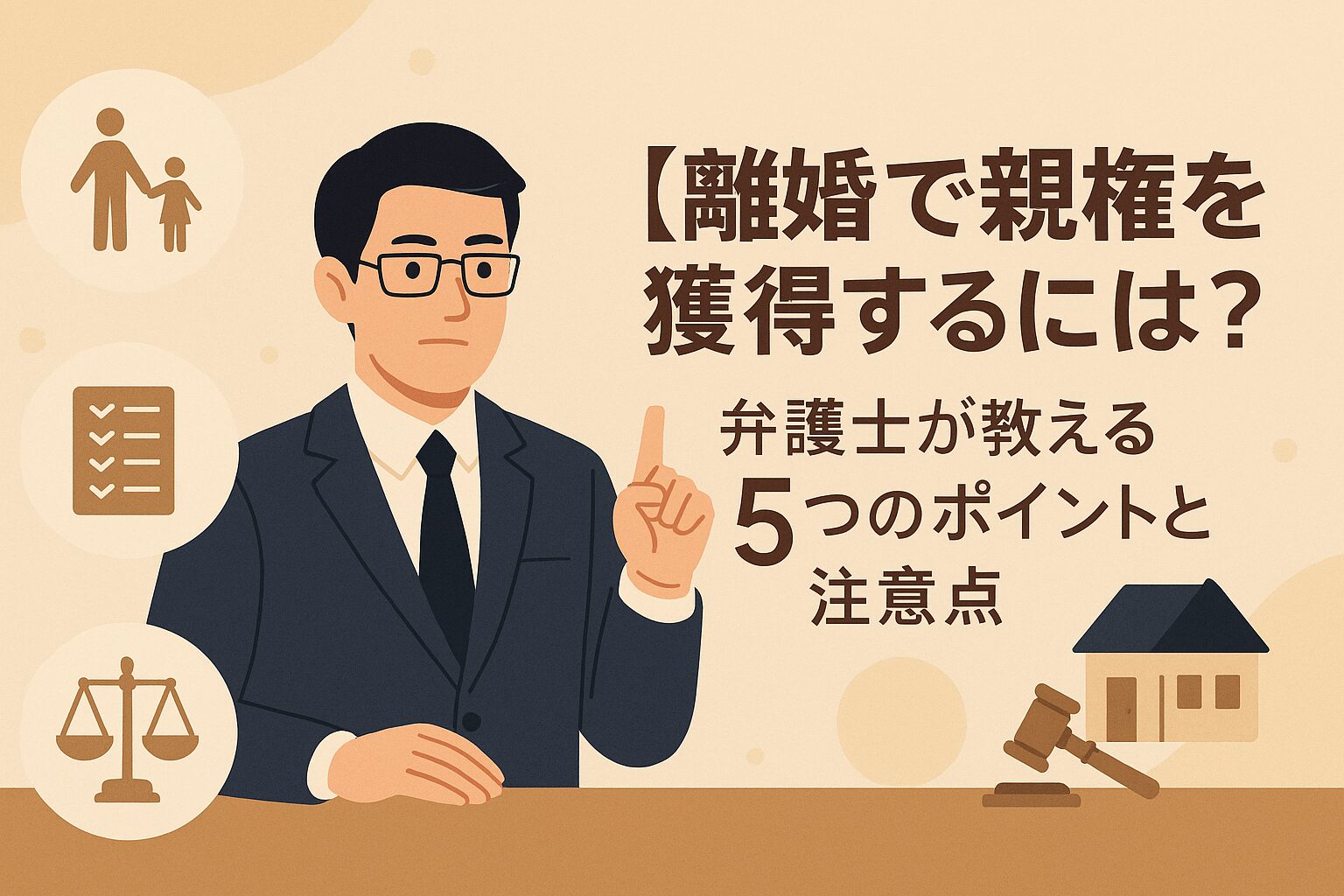「離婚は仕方ないけれど、子どもの親権だけは絶対に譲れない…」
「親権を確実に獲得するためには、何をすれば有利になるの?」
「母親の方が有利って本当?父親が親権を取るのは難しい?」
お子さんがいる夫婦の離婚において、「親権」をどちらが持つかは、最も重要で、そして最も感情的な対立を生みやすい問題です。お子さんの将来を想うからこそ、その親権を巡る争いは、時として泥沼化してしまうことも少なくありません。
親権争いを有利に進めるためには、感情的に自分の主張をぶつけるのではなく、裁判所が何を基準に親権者を判断するのかを正しく理解し、その基準に沿って、ご自身が親権者としてふさわしいことを客観的な事実で示していく必要があります。
この記事では、お子さんの親権を心から願うあなたが、後悔のない選択をするために、法律の専門家である弁護士監修のもと、以下の点を詳しく解説します。
- そもそも親権とは?裁判所が判断するたった一つの基準
- 【最重要】親権獲得の可能性を高める5つの必須ポイント
- これをやったら不利になる!親権争いで絶対にやってはいけないこと
- 親権獲得における弁護士の重要な役割
- 親権に関するよくある質問
この記事を読めば、親権争いの本質を理解し、お子さんの未来のために、あなたが今から何をすべきか、そして何をすべきでないかが明確になります。正しい知識を身につけ、冷静に、そして戦略的に行動しましょう。
目次
親権とは?裁判所が判断するたった一つの絶対的な基準
まず、離婚における「親権」が何を意味するのか、そして裁判所が何を最も重視するのかを理解しておきましょう。
親権の2つの要素
日本の法律では、離婚後の親権は父母のどちらか一方のみが持つ「単独親権」が原則です。親権には、大きく分けて以下の2つの権利・義務が含まれます。
| 権利の種類 | 内容 |
|---|---|
| ① 身上監護権(しんじょうかんごけん) | 子どもの世話や教育、しつけを行い、心身の成長を図る権利・義務。 (例:食事の世話、学校行事への参加、病気の際の看病など) |
| ② 財産管理権(ざいさんかんりけん) | 子ども名義の財産(預貯金、相続財産など)を管理し、法的な契約行為を代理する権利・義務。 |
通常、親権者がこの両方を持つことになりますが、稀に、身上監護権を持つ「監護者」と、財産管理権を持つ「親権者」を分けるケースもあります。
裁判所が判断する絶対的な基準:「子の福祉」
親権について夫婦の話し合いがまとまらない場合、最終的には家庭裁判所の調停や裁判で決めることになります。その際、裁判所が親権者を判断する基準は、たった一つです。
どちらの親に監護されることが、子どもの健全な成長と幸福にとって最も望ましいか(=子の福祉)
裁判所は、「離婚の原因はどちらにあるか」「どちらが経済的に豊かか」といった親側の事情よりも、徹頭徹尾、子どもの視点に立って判断します。したがって、親権を獲得するためには、「私がいかに親権者としてふさわしいか」ではなく、「私と暮らすことが、子どものためにいかにプラスになるか」を具体的に主張・立証していく必要があるのです。
【最重要】親権獲得の可能性を高める5つの必須ポイント
では、「子の福祉」の観点から、裁判所は具体的にどのような要素を重視するのでしょうか。親権獲得の可能性を高めるために、あなたが実践すべき5つの重要なポイントを解説します。
| ポイント | 裁判所の視点 | あなたが実践すべきこと |
|---|---|---|
| ① これまでの監護実績 | 【継続性の原則】これまで主として子どもの世話をしてきた親に、引き続き任せるのが子の環境変化が少なく望ましい。 | 食事、入浴、寝かしつけ、送迎、学校行事への参加、病気の際の看病など、日々の育児への関与実績を具体的に示す(育児日記など)。 |
| ② 子どもと過ごせる時間 | 今後、子どもと直接関わる時間を十分に確保できるか。 | 仕事と育児を両立できる具体的なプラン(時短勤務、在宅ワーク、ベビーシッターの利用など)を提示する。 |
| ③ 監護への協力体制 | 親自身が病気や多忙の際に、育児をサポートしてくれる存在(祖父母など)がいるか。 | 両親や兄弟姉妹からの協力約束を取り付け、具体的にどのようなサポートが得られるかを示す。 |
| ④ 面会交流への姿勢 | 【フレンドリーペアレント・ルール】離婚後、子どもと離れて暮らす親との交流を、積極的に認めようとしているか。 | 相手への不満があっても、子どもから片方の親を奪うような言動は慎み、具体的な面会交流のプランを提案する。 |
| ⑤ 子どもの意思 | 子ども自身が、どちらの親と暮らしたいと思っているか。 | (特に10歳以上の場合)子どもの気持ちを尊重する姿勢を見せる。無理に意思を誘導しない。 |
ポイント①:主たる監護者としての「監護実績」を積み重ね、記録する
これが最も重視されるポイントです。裁判所は、環境の大きな変化が子どもの負担になると考え、「これまで主に育児を担ってきた親」を優先する傾向が非常に強いです(継続性の原則)。
これを客観的に示すため、別居前から、そして別居後も、「育児日記」をつけることを強くお勧めします。食事の準備、保育園や学校の送迎、寝かしつけ、病気の際の看病、学校行事への参加など、日々の育児への関わりを具体的に記録しておくことで、あなたが主たる監護者であることを示す強力な証拠となります。
ポイント④:相手親との「面会交流」に協調的な姿勢を示す
意外に思われるかもしれませんが、相手への敵意をむき出しにし、「子どもには絶対に会わせない」というような排他的な態度を取ることは、親権争いにおいて著しく不利に働きます。
裁判所は、離婚後も子どもが両方の親から愛情を受けることが「子の福祉」に資すると考えています。そのため、相手の親と子どもの面会交流に寛容で、積極的に協力しようとする親(フレンドリーペアレント)の方を、親権者としてふさわしいと判断する傾向があるのです。相手への感情は一旦横に置き、子どものための面会交流には協力的な姿勢を示しましょう。
これをやったら不利になる!親権争いで絶対にやってはいけないこと
親権を獲得したい一心で取った行動が、逆にあなたを不利な立場に追い込んでしまうことがあります。以下の行為は絶対に避けましょう。
| NG行動 | なぜ不利になるのか |
|---|---|
| 相手の同意なき「子どもの連れ去り」 | たとえ親であっても、一方的に子どもを連れて家を出る行為は「違法な連れ去り」と見なされ、親権者としての適格性を著しく疑われる原因となります。 |
| 正当な理由なき「面会交流の拒否」 | 相手を困らせるためだけに面会交流を拒否すると、「子どもの気持ちを考えていない自己中心的な親」と判断され、不利になります。 |
| 子どもへの「相手の悪口」の吹き込み | 子どもを自分の味方につけようと、相手の悪口を吹き込む行為は、子どもの精神的成長を害する「心理的虐待」と見なされる可能性があります。 |
| 調停や裁判での「虚偽の主張」 | 相手を貶めるために、事実でないDVや虐待を主張するなど、嘘をつくことは、後に発覚した場合にあなたの信頼性を完全に失わせ、極めて不利な結果を招きます。 |
親権獲得における弁護士の重要な役割
親権争いは、感情的な対立が激しく、法的な専門知識も不可欠なため、弁護士のサポートが極めて重要になります。
- 客観的な状況分析と戦略立案: あなたの状況を冷静に分析し、「子の福祉」の観点から、親権を獲得するために何をすべきか、何をすべきでないか、具体的で効果的な戦略を立てます。
- 有利な証拠収集のサポート: 育児日記の付け方や、監護実績を示すための証拠(保育園の連絡帳、写真など)の集め方について、法的な視点からアドバイスします。
- 相手方との交渉代理: あなたの代理人として、感情的にならずに相手方やその代理人弁護士と冷静に交渉を進めます。
- 調停・裁判での専門的な主張: 家庭裁判所の手続きにおいて、あなたの監護能力や監護への意欲、今後の養育環境などを、説得力のある書面(主張書面)として作成し、法廷で的確に主張します。
よくある質問(FAQ)
Q. 離婚原因(不倫など)は、親権の判断に影響しますか?
A. 原則として、直接影響しません。例えば、「不倫をした親=親権者としてふさわしくない」とは、必ずしもならないのです。裁判所が見るのは、あくまで「どちらが子どもの世話をするのに適しているか」という点です。ただし、不倫にのめり込んで育児を放棄していた、といった事情があれば、当然不利に考慮されます。
Q. やはり母親が親権を取るのに有利なのでしょうか?
A. 乳幼児期の子どもについては、母親との情緒的な結びつきが重視される「母性優先の原則」が考慮される傾向はあります。しかし、子どもが成長するにつれてこの傾向は薄れ、父親であっても、これまで主たる監護者として育児を担ってきた「監護実績」があれば、親権を獲得することは十分に可能です。
Q. 私の方が収入が低いのですが、親権争いで不利になりますか?
A. 収入の多寡が親権の判断を直接左右することはありません。なぜなら、子どもの生活費は、相手方から支払われる「養育費」で補うことができるからです。収入が低いことよりも、安定した収入を得て、子どもとの生活を維持していく具体的な計画があることの方が重要です。
Q. 一度決まった親権を、後から変更することはできますか?
A. 可能です。ただし、そのためには、親権者を変更することが「子の福祉」にかなうと認められるだけの「事情の変更」(例:親権者の長期入院、虐待、育児放棄など)が必要であり、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。一度決まった親権を変更するのは、決して簡単ではありません。
まとめ:子どもの未来のために、最善の選択を
離婚時、そしてその後の子どもの人生において、親権がどちらになるかは、計り知れないほど大きな影響を与えます。
親権者を決める唯一の基準は、どちらの親と暮らすことが「子の福祉」に最も貢献するか、という点です。その判断は、
- これまでの監護実績
- 今後の監護体制
- 面会交流への協力的な姿勢
といった、具体的で客観的な事実に基づいて行われます。
感情的な対立の中で、これらのポイントを一人で冷静に主張・立証していくのは至難の業です。また、「連れ去り」や「面会交流の拒否」といった誤った行動は、あなたを致命的に不利な立場に追い込む可能性があります。
お子さんとの未来を確実なものにするため、そして何より、お子さんにとって最善の選択をするために、親権に争いがある、あるいは争いになりそうな場合は、できるだけ早い段階で、離婚問題に精通した弁護士に相談することを強くお勧めします。
☑豊富な借金問題の解決実績
☑債務整理のエキスパート
☑クライアントに本気で寄り添う
☑あなたに合った解決方法を見つけられる
\専門家による本気のアドバイス/